デンマークでドイツ系の両親のもとに生まれ、主にフランスで活躍したフランク。この作曲家の名前を知っている人はそうは多くないはずである。今回初めて知ったという人もいるのだろう。その残した作品の数からして数えるほどしかなく、加えてその曲の内容が、一般受けのしない、地味なイメージといおうか図式的といおうか、とにかくとっつきにくい作風と理解されがちだからである。
しかし、クラシックファンの間ではフランクといえば独自の世界を切り開いた作曲家として名高い。特に後に述べる「循環形式」という優れた音楽形式を確立した、クラシック界の重鎮である。とにかくその独特なハーモニー、決して派手にならない内燃するエネルギー、段階を踏んで丹念に作り上げられる形式美、そして彼の信仰から湧き起こる神への讃美。外面のきらびやかさはないものの、フランクの音楽には誰もが深い共観を覚えずにはいられない音楽性がぎっしりつまっている。
さて、フランクをほめそやしてばかりいるが、ではこの作曲家は一体どのような人物なのだろうか。
彼の弟子の一人デュパルクの生徒(つまりフランクの孫弟子)が、フランクについての評を残している。彼は幼いころから才能を発揮するいわゆる「神童」形の人間ではなかったという。自分なりに努力をし、自分なりの音楽性を磨き、自分で自分をたたき上げるいわゆる努力型の人間であった。そして作曲家として遅咲きでしかも地味な存在になったのは、自分でなっとくするまで曲を練り上げ、誰がほめてくれなくてもいい、その曲が自分の思い通りの音色となって響き、神がそれをみとめて下さることだけを望む人だったからである。
彼が目標とする人物は、彼が幼いころに没したベートーヴェン、同世代のブルックナー、そして誰よりも畏敬の念をあらわにしていたバッハであった。特にバッハの研究にかける情熱にはものすごいものがあり、おしくも失われてしまった楽譜を全国を巡り歩いて集めるという不可能を成し遂げようとしたりもした。それはともかく、上の3人の作曲家の共通点を見出せば、自然とフランクの人となりも明らかになる。まず彼は深いドイツの精神に根ざした音楽を探し求めた。次に彼はオルガンの名手を目指した(もっともベートーヴェンは同じ鍵盤楽器でもピアノの名手であったが)。そして何よりも大切なことが、常に主イエスに近づくことを忘れない敬虔なキリスト者であろうとした。実にフランクは、ドイツ風の音楽をオルガン的な厚い響きで荘重に鳴らし、聴き手を宗教的な気持ちに導く作曲家なのである。
彼のこの謙虚な人間性、朴訥で飾らない態度、実直でひたむきな音楽への情熱は多くの人々から支持された。そして彼の音楽にあこがれ、弟子になろうとする若者が後を絶たなかった。そしてこれらの人々は自然とその一派を形作っていった。これがいわゆる「フランキスト」である。フランキストの特徴は、「循環形式」をベースとして、オルガンの響きを思わせる層の厚い音色を使いながら、静かなるところから音楽をはじめ、次第に盛り上げはするものの決して鋭い響きにはせず、また静けさに帰っていくという、いわば「聖なる音楽」という言葉がぴったりくるものである。
さて、先ほどから「循環形式」なる言葉を使っているが、これは一体どのようなものなのか。
一口でいってしまえば、ある特定の主題が曲の中で何度も現われ循環する形式のことである。主題を循環させる音楽といってすぐ思いつくのが、ベートーヴェンの「運命交響曲」である。曲の最初に現われる「ジャジャジャジャーン」という有名な主題が、曲中それこそ何百回も繰り返され、大交響曲を作っていく。しかしこの場合は一般的に「循環形式」とはいわない。主題そのものが2小節しかない断片だからである。
このベートーヴェンのすぐ後の作曲家、ベルリオーズはこの考えを発展させ「固定楽想」という形を打ち立てた。物語をもった「幻想交響曲」の中で用いている。そしてクラシックファンならご存知と思うが、この「固定楽想」の影響を受けたワーグナーがさらに、みずから考え出した「示導動機」というものを楽劇の中で駆使している。「固定楽想」も「示導動機」も、特徴的なメロディをある特定の役柄、例えば物語の中のヒロインならヒロインにあてはめ、曲の中で象徴的に使っていく、というものである。
フランクの「循環形式」は、物語のない交響曲のような純音楽の世界で、特徴のあるメロディを何度も、時には楽章をまたいで登場させ、曲全体の統一を図ろうとするものである。こうすることにより、曲の初めに登場した主題が途中さまざまなメロディーにもまれながらも、あるとき突然昔をなつかしむように再度登場することになり、聴き手は何か郷帰りをしたような、人間の原点に立ち返らされたような感覚にとらわれる。それがフランク独特の崇高ともいえるハーモニーに彩られていて、信仰的な喜びを感じる結果となるのである。
今回の「交響的変奏曲」も循環形式による音楽である。普通、変奏曲といえば一つの主題が示され、それをもとにしたそれぞれに違う彩りのある変奏が何回か繰り返されるというものである。この曲もそうした構想を念頭に置いてはいるものの、表面上で聞こえる音符の変化だけではなく、もっと奥の深いところ、いわば調性や和音というような内部的なところで変容が試みられており、しかも主題が一つではなく複数という関係上、その主題同士が複雑に、しかし見事に絡み合いながら曲を進めていくのである。
楽器編成としては、独奏ピアノとオーケストラの共演という形をとっている。曲中にカデンツァ(独奏者がソロで華麗なテクニックを披露する部分)も置かれていることから「協奏曲」としてもよさそうなものであるが、協奏曲の形式よりもフランクみずからが考案した循環形式を重んじたいがために結果的に「変奏曲」としたのであろう。また、シューマン風なタイトルで「幻想曲」あるいはラフマニノフのように「狂詩曲」として自由なイメージを持たせてもよさそうなものであるが、フランクは曲の形式をそこまで崩したくはなかった。つまり「協奏曲」の形式にはおさめず、しかも「幻想曲」「狂詩曲」まで自由な展開も持たせず、やはりフランクにしか作れない循環形式による変奏曲として発表したのがこの「交響的変奏曲」なのである。
彼の思いを終結させたこの曲はしたがって俗受けする音楽ではない。しかし自分の思い通りの曲を書き上げることができたフランクはさぞかし満足したことであろう。
おわかりのようにフランクの音楽に面白おかしい題材はない。「カルメン」「新世界より」「モルダウ」「ボレロ」といったなかばポピュラー化したクラシックとはまったく性格を異にするものである。いってみれば、いぶし銀の音楽、通をうならせる作曲家といったらよいであろう。聴くときには予習をしたり解説書を片手にということも必要になってくる。しかしながら、彼の音楽を聴き終えたときには、その労力をおぎなって余りある、普通では得られないような感動をおぼえることができる。まるでオルガンのようなぶ厚い音色、うねるような感情の満ちひき、♯(シャープ),♭(フラット)を使った独特な和音と半音進行、まるで故郷に戻るような「循環形式」の扱い・・・。おおげさでなく、フランクの音楽を聴いたときには生きる喜びといおうか、キリスト教的にいえば、まるでいながらにして神のみもとに引き上げられるような精神の昂揚を体験することができる。
フランクに関してはこの限られたスペースで語りつくすに無理があるので、いずれまたこのコーナーで取り上げてみようと思う。今回は「交響的変奏曲」でお付き合いいただきたい。
曲はまず、オーケストラで、力強いが暗いかげのある主題(以下A)が出され、続いてピアノがやわらかいメロディー(以下B)を示す。このオーケストラと独奏ピアノの素晴らしいかけあいで盛り上がったあと、弦楽器のピチカート(弦を指ではじく奏法)にのって管楽器のはねるような主題(以下C)が静かに表われる。
これらのA,B,Cがその後の循環形式のモティーフになるものなので、よく覚えておいていただきたい。
独奏ピアノが華麗な技巧をもってBを再度演奏し終えてからが変奏の始まりである。
第一変奏はチェロとコントラバスが静かにAを演奏して始まる。ここは、チェロのBの演奏と管楽器のCの演奏が混ざり合ったりと、聴きごたえのある部分である。
Cの展開に始終する第二変奏。ピアノとオーケストラのかけあいが素晴らしいが、それにも増して木管とのからみ、弦楽器との混ざりあいなど、考えられる限りの変奏を展開している。和声もフランクらしい非常に高貴なもので、彼の内面、信仰を感じることができる感動の一瞬である。
第三変奏の主役はチェロである。今まで技巧を凝らしていたピアノが今度は伴奏楽器として扱われ、その上でチェロがCを表情豊かに歌う。
第四変奏はこれまた趣向をこらした部分で、前部分のおしまいにホルンがリズミカルに出たかと思うと、ピアノとオーケストラがABCを同時に変奏する。
そして曲はクライマックスをむかえる。ピアノがあらためてCを演奏したかと思うと、オーケストラが沈黙し、Bをもとにした第五変奏をピアノが独奏で奏する。いわば協奏曲のカデンツァに当たる部分である。非常に表情が豊かで同時にテクニカルで、聴けば聴くほど味わいの出てくる不思議な部分、そして独特なハーモニーと巧みな循環形式によってあたかも信仰に帰依してしまうかのような曲想である。
この第五変奏の後、オーケストラが負けじと表われ、ピアノと「競奏」をくり広げながら素晴らしい終結部をむかえるのである。
おすすめCD
THE BEST
ホルヘ・ボレット(ピアノ)
リッカルド・シャイー指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団[ロンドン]
名曲にもかかわらずCDが極端に少ない。お堅いと思われがちなクラシックのなかでも特に「お堅い」イメージがあるからだろう。今回の執筆にあたりあらためてCDショップを3・4店まわったが、残念なことに1枚も見当たらなかった。
ということで筆者が耳を傾けたことのある録音(カセット)は上のものだけになってしまう。
寸分のすきも見せない名指揮者シャイーが、彼とベストコンビを組んでいるコンセルトへボウと、激しすぎずおとなしすぎずの名演をくり広げている。それをバックに、ボレットがこまやかなタッチでフランクの世界を描き出している。キューバ出身のボレットはリストのような鮮やかで技巧的な演奏を得意とするが、この曲のように内向的精神的な曲も巧みに演奏する。やはり名ピアニストなのである。一口に協奏曲といっても、ソロとオーケストラがうまくブレンドしあう「共演」、ソロがオーケストラを引っ張って(?)いく「協演」、ソリストと指揮者の個性が激突する「競演」とさまざまだが、この演奏は、シャイーとボレットがお互いの持ち味を尊重しあう「共演」タイプだと思う。聴き終えたあとに爽やかな感動をおぼえることができる。
その他、下のCDは、評論家の志鳥栄八郎氏と出谷啓氏がともに推薦しているもので、こちらは明るい音色とダイナミックな表現を特徴とする「きわめつき」の名演奏らしい。「競演」の部類に入るだろうか。
薦めている曲のCDがなかなか店頭に見当たらないのだから心苦しいが、読者の皆さんにはこれらの録音でなくてもよいから「交響的変奏曲」をぜひ一度聴いていただきたい。
下もおすすめ
カサドシュ(ピアノ)
オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団[CBS・ソニー]
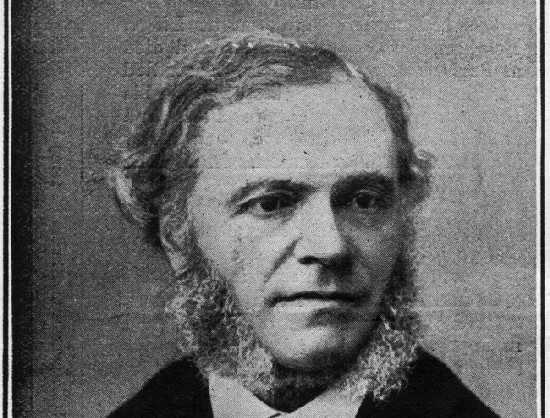


コメント