芸術家が他分野の芸術から霊感を受け、自分の作品にそれを反映させるということはよくあること。舞台監督が彫刻作品を鑑賞し、そこからふくらんだイメージを自分の作品に取り入れたり、あるいは詩を読んだ画家がそのテーマをもとに筆を進めるという具合に、一見なんのつながりもなさそうに見える分野同士が芸術という名のもと深いところで影響を与え合っているのはよくあることである。
私たち日本人が海外に大いに誇れることとしては、フランスで発祥した印象派が実は日本の文化から大きな影響を受けていたことであろう。印象派絵画の巨匠といわれるモネの一連の作品「睡蓮」はまさに浮世絵と日本庭園から霊感を受けて描かれたものである。また音楽の印象派でいえば、ドビュッシーの代表作、交響詩「海」は、印象派絵画から影響を受けて作曲されたようにいわれることもあるが、あの作品こそ、葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」から霊感を受けて作曲されたものである。とかく芸術作品は他の作品から影響を受け、またそのように刺激しあうことによって素晴らしい作品が生れるものである。
音楽の世界はどのような芸術ジャンルから影響を受けているだろうか。上のドビュッシーのケースのように、絵画から受ける場合も少なくはないが、やはり一番多いのが文学や詩の世界からの影響だろう。世界最大の文学、聖書は別格として、いちいち見ていてはきりがないのでいくつかの例にとどめるが、シェークスピアやシラーの作品に触発されたベートーヴェン、ゲーテなどの詩にイメージをふくらませたシューベルト、「マクベス」やニーチェの「ツァラトゥストラ」を交響詩として描いたリヒャルト・シュトラウス、「ファウスト」「ロメオとジュリエット」などにいたっては何十人という作曲家が音楽を附けている。このように音楽の世界は音楽自体がイメージの産物ということもあり、文学界から影響を受けた例は枚挙にいとまがない。
さて、それでは逆のケースとして、音楽が他の芸術に影響を与えることはあるのだろうか。さすがにこちらの例は少ない。筆者が記憶する限りでは舞台芸術に影響を与えることが多いようで、例えばショパンのピアノ曲をオーケストラ用に編曲し、そこにバレーを振付けた「レ・シルフィード」や、最近ではラヴェルの「ボレロ」がモーリス・ベジャールなどの手によって様々な「ダンス」として踊られている。しかし、「ボレロ」も元来は純粋なコンサートのための曲ではなくバレー用として作曲されたことを考えると、舞台に影響を与えたとは考えにくい。やはり音楽というものはそれ自体抽象物であるがゆえに、他から影響を受けることはあっても他に影響を与えることはめったにないようである。
さて、ロシアの作曲家チャイコフスキーの作品は、切なくなるような甘いメロディとロシア特有の荒々しい曲想とが同居するもので、彼の曲こそ他分野の芸術に影響を与えそうなものである。ロシアの作曲家としては珍しく、ドイツ・オーストリアの伝統音楽を積極的に学んだため、ロシア音楽にも西欧音楽にも徹しきれていない音楽家などと非難が飛んだりはするが折衷主義作曲家として評価は非常に高い。特に母国ロシアでは想像できないような人気があり、国内の人々、特に芸術家には多大な影響を与えた。なかでも文豪トルストイは彼に傾倒し、深い交友関係を結んでいたし、彼の音楽から不思議なインスピレーションを受けては自分の作品に反映させていた。音楽が他分野に影響を与えた数少ない例である。
今回の弦楽四重奏曲第1番はとりわけトルストイが愛した曲である。一つの有名なエピソードがある。1876年の暮れ、チャイコフスキーが教授を務めていたモスクワ音楽院にトルストイが訪れ、歓迎の演奏会が行なわれた際にこの曲も演奏されたが、列席していたトルストイはその第2楽章「アンダンテ・カンタービレ」の甘美なメロディが始まるとたんに中を仰ぎ、曲が進むにつれて涙を流し始め、楽章が静かに終わるところではまともに座っておれずに泣き伏していたという。そして言葉ではいいあらわせないような感銘を受けたトルストイはすぐさま、その感動を著す決心をする。ちょうどそのころに書かれたのが有名な「光あるうち光の中を歩め」である。原始キリスト教時代を舞台に、社会的成功を求めてやまない男ユリウスと、キリストの教えを忠実に守る男パンフィリウスとを対照的に登場させることにより、トルストイのキリスト教感をあますところなく書きつづったこの傑作は、「アンダンテ・カンタービレ」の甘い、しかし寂しさ厳しさも持ち合わせる響きから文章が生み出されるとしたら、ちょうどこのようなものになるのではないか、と思わせるような文学である。特に物語もなかばをすぎたあたりで、パンフィリウスの、結婚に対する美徳にも近い考え方や人間の才能は神のご意志の遂行のために捧げるべきだという意見に、ユリウスが「君が描き出す生活の美しさはすべて欺瞞(ぎまん)にすぎない」と反論する場面がある。この反論を受けてのパンフィリウスの言葉「全身全霊をあげて真理の認識・天なる父との交感を求めているひとびとは、真の幸福を求むるひとびとはですね、―そうしたひとびとはどうしてもキリストの歩んだ道にいたらざるをえないし、したがって、彼のあとにつき、自分の行く手に彼の姿を認めずにはいられないのです。(中略)キリストは神の子だ、神と人類との仲介者だ。(原久一郎氏訳=新潮文庫)」の行間を読むとき、トルストイ自身が何か大きなものに心を動かされてこの書を書いたに違いないという気がしてならない。トルストイは「アンダンテ・カンタービレ」から感動を受けた結果、自分のどの作品にどのように反映させたか明記はしていない。しかし、演奏会の直後に書いた次のような手記がある。「かの(第2楽章の)神々しい調べが私の耳に響いてきたとたん、私は至福を感じ、身震いした。いや、身震いというのは正しくない。何かを心の奥から吐露せずにはおれないような力が湧き起こり、今にも噴火せんばかりの、精神が揺れ動かされるような感覚におちいった。この調べが橋渡しとなって天上の神が私の心に入り、私は神のものとなった。」 これを読む限り「アンダンテ・カンタービレ」が「光あるうち光の中を歩め」に影響を与えたことは想像に難くないのである。トルストイのあの名作はこのようにして生まれたのであった。チャイコフスキーはクラシック音楽家の中でも特に優れたメロディメーカーである。ロシア人らしい無骨な一面も見せるピアノとヴァイオリンそれぞれのための協奏曲、悲痛と絶望の世界を展開する「悲愴」交響曲、おとぎの国を描いた優美さこの上ない3大バレーなど、チャイコフスキーはそのときどきに応じていろいろな側面を見せるが、共通していえることは、彼の作品を支えているのは万人を感動させるそのメロディである。
今回の弦楽四重奏曲第1番そのものは、上にあげた曲ほどの人気は博していない。弦楽四重奏曲それ自体が比較的地味な存在だからということも考えられる。しかし何かを切々と訴えるようなチャイコフスキー独自の楽想が随所にちりばめられていて、じっくり聴いていると身体が吸い込まれていくような錯覚にとらわれてしまう。トルストイが思わず涙した理由も十分理解できるのである。
なお、この曲自体にはもともと名前はついていない。しかし今回は「アンダンテ・カンタービレ」を中心に書いているので、正しい呼び方ではないのだが曲そのものにニックネームとしてつけさせていただいた。
——————————————————————————–
曲について
第1楽章
何かとらえどころのないような揺れ動く第1主題が始まる。8分の9拍子という風変わりなテンポ設定のうえ、シンコペーションも使われているのでなかなかこのオープニングに親しめない人もいるかもしれないが、このような雰囲気こそチャイコフスキーの魅力なのである。繰り返し聴くと頭から離れなくなる第1主題である。途中、この第1主題と同じリズムの第2主題も奏されるが、主に第1主題を急速にしたり情熱的にしたりとこの主題の展開に集中する。
第2楽章「アンダンテ・カンタービレ」
もういうまでもなくこの弦楽四重奏曲第1番の中の聴かせどころである。それどころか、数多いチャコフスキーの華麗なオーケストラ曲に一歩もひけ をとることなく、小さいながらも宝石のような光を放っている名楽章である。「アンダンテ・カンタービレ」とはご存知のとおり「歩く速度で、歌うように」という音楽用語だが、曲があまりにも有名になってしまったためかタイトル化してしまった感がある。
まずヴァイオリンで、長調ではあるが寂しげな主題が出る。厳しいロシアの寒さを暖炉で和らげているような、昔を懐かしみひとり民謡を歌っているような、永遠にかなうことのない憧れを夢見ているような、いろいろな思いが交錯する。あまり気づかないことだが、この主題も4分の2の中に4分の3が混ざるという変則的なテンポをとる。主題は何度も繰り返されそのたびごとに厚みを増していく。トルストイが泣きくずれた部分である。
チェロのピチカートでリズムが刻まれるところからが中間部である。ここでもまたヴァイオリンが甘く寂しげな主題を提示する。単純な音形にもかかわらずこれがまたチェロの低音部と混ざり合って感動的である。
最初の主題が戻ってきて、さまざまな色で塗り替えられる。あるときは感動的に、あるときはごく静かに。そして最後は力なく消え入るような終わりをむかえる。
第3楽章
前の楽章とははっきりとしたコントラストをつけ、ここには鋭いリズムをもつ急速な3拍子の楽章を持ち込む。長調の「アンダンテ・カンタービレ」が寂しい雰囲気に包まれているのに対し、短調のこの楽章の方が楽しげなのもまたおもしろい。この楽章でもまたはじめに出た主題が何度も繰り返され、エネルギッシュに展開されていく。
第4楽章
このフィナーレにきてようやく気分が晴れやかになる。はじめの2つが静かな楽章で次が短調の楽章であっただけに、勢いのいい長調のこの楽章は非 常に新鮮に聞こえる。まずヴァイオリンに爽やかな第1主題が現われるが、ここでもまたこの主題をさまざまな形に展開することに始終する。飛び跳ねるような第2主題も楽章に変化を与えている。最後はさらに勢いを増し、なごり惜しそうに何度も何度も音を引っ張りながら、分厚いハーモニーのうちに全曲が閉じられる。
おすすめCD
THE BEST
ガブリエリ弦楽四重奏団[ロンドン]
現在のところ、一番無難な線でおすすめできるのが上のCDである。前半と後半の楽章の緩急の差をはっきりつけ、実にメリハリのきいた演奏になっている。「アンダンテ・カンタービレ」の部分では、終盤の静かな箇所で感傷的になりすぎているのでは、といった印象もなくはないが、このくらいやってもらったほうがチャイコフスキーの真髄に触れているような気がする。またこの曲の場合、2楽章が終わったときには、そのごく静かな雰囲気をこわさないようにしながら思い切りいい次の楽章に移らなければならないが、そのあたりの間のとり方(秒数といったようなことではなく、音量と奏法)が実にうまい。普通に聴いていると聴き流してしまうような芸の細かさに注目したい。
下もおすすめ
ボロディン弦楽四重奏団[RCA]

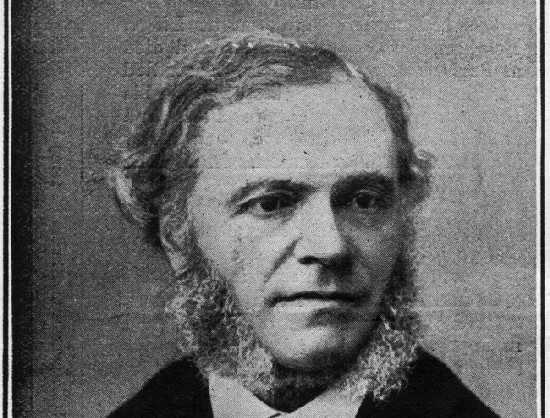

コメント